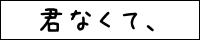
St.バレンタイン
二月十四日。
「チョコレート会社の戦略だ」と斜に構えてみてもはじまらない。こういう時はのっかったもの勝ちだ。使えるものはすべて使って、恋の勝者になる! それが大事なのよ。いつだったかテレビタレントがバライティー番組で言っていた。
「恋を楽しまなくちゃね」
そんなことも言っていた。
――恋を楽しむ。
掌にのるほどの小さな箱。ベッドに寝転んで、それを眺める。中身はチョコだ。味はビター。「甘いものが苦手な人にもオススメです」と販売店のポップに書かれていた。スイーツ男子が流行らしいけど、甘いものが苦手な男性はやはり多い。彼もまた。渡しても食べてはもらえないだろう。わかってはいるけど、つい、買ってしまった。
――今年こそはちゃんと渡したい。
心に決めていたのに、こういう日に限って朝から晩まで仕事で家にいない。何かの牽制なのかと妙な勘ぐりをしてしまう。心が折れそうだ。
ダメだ、ダメだ、そんな弱気では。今年は去年までとは違う。私たちは恋人になったのだから、堂々と、胸を張って渡せる。そうやって何度も自分を奮い立たせた。
手渡すなら今日中に渡したい。やはりイベントごとはイベント当日に渡すことが大事だ。帰宅時間は午後十時と聞いている。チャンスはある。ただし、予定に狂いがでなければという条件つきだ。だがその条件が問題だった。仕事柄予定などあってないようなものだ。実際、告げられた時間に帰ってくる方が少ない。
「今日中には渡せそうにないかも……」
彼は仕事なのだ。無事に戻ってきてくれるだけでも感謝しなければならないぐらいだ。けど……。本日、幾度目かのため息がこぼれた。
***
「お待ちしておりましたわ」
体のラインを強調した黒いドレス。口紅は真っ赤で妖艶だ。己の美貌をあますことなく理解し、最も効果的に見せる術を心得ている。こういったタイプは嫌いではない。欲望に忠実なことを隠そうともしない潔さは悪くない。ただ、それが自分に向けられると話は別だが。
嬉しそうに微笑む女に促されるまま、ソファに腰を降ろした。
「……今宮氏の姿が見えませんが」
「お父様は来ませんわ。本日、陽芽様をお呼びしたのは私ですもの」
なんとなくそんな予感はしていたが、やれやれと思った。
「お嬢様が私にどんな御用でしょうか?」
極めて義務的な声を出すが、女は「意地悪!」と拗ねた顔をしてみせた。逆効果だったらしい。
「陽芽様に御提案がありますの。悪くないお話だから、きっと気に入ってもらえると思いますわ」
ろくな提案ではなさそうだな、と思ったが、聞かずには帰れそうもない。とりあえず先を促した。
「私と結婚していただきたいのです。……女の方からこんなこと申し上げるのはどうかしら、と思って今まで黙っていたのですけど」
朱乃のことを知って、悠長なことを言っていられなくなった。ということだろう。
「私なら、陽芽様のことを支えて差し上げられますわ」
経済的な面で。それは間違いない。女と婚儀を結べばかなりの利にはなる。
「……なるほど。確かに悪くないお話ですね。ですが生憎、私にはもうすでに相手がいますので」
「私、愛人の一人や二人いても、目くじらなんてたてません」
その発言は疑問だ。自分に惚れさせる自信がある。だから強がって見せているだけで、実際には嫉妬深い性格だろう。本当に愛人がいたら、おそらく許さない。
「その女性だって、陽芽様のためになると思えば、多少の我慢はするはずです。そうでないなら本当に陽芽様を愛しているとは言えませんわ」
勝手な言い分だな、と思った。朱乃の気持ちを疑われるのも、ましてつまらない女と判断されるのも気分が悪い。だが、女は、俺の地雷を踏んでいることに気づいてはいない。期待に芽を輝かせていた。今まで、すべて思い通りになってきたお嬢様だ。
「そうですね。朱乃は出来た女です。私がそのことを告げれば、彼女は従ってくれるでしょう」
「でしたら――」
「ですが、私が納得しません。朱乃以外の女を必要としない。たとえそれがどんなに利になろうと」
「――っ」
女の顔色が一瞬で変わる。真っ赤になって口を開きかけた、その時、
「お前の負けだ。諦めなさい」
「……!」
入ってきたのは今宮氏だった。
「お父様!」
「これ以上、無様な姿をさらしたいのか」
「……」
女はそのまま勢いよく部屋を出ていった。代わりに、今宮氏が女の座っていた場所へ腰をおろした。女の父親にしてはいささか年をとっている。遅くに生まれた一人娘。可愛くて仕方ないのだろう。
「すまなかったね。わがままに育ててしまって。君には決まった相手がいるからと何度も言ったのだが、説得してみせるからと聞かなくてね。それで断られたら諦めるだろうとこんな場を持たせてもらったのだが」
内心では娘と俺がうまくいけばそれはそれでありがたいと思っていたのだろう。そんな含みを感じた。
「ご期待に添えなくて申し訳ありません」
「いや、こちらこそ不粋な真似をした。こんなことを言うと親バカだと思われるかもしれないが、けして悪意があったわけじゃない。許してやってほしい。恋は人を変えてしまうから」
「はい、それは」
恋が人を変えるのは身を持って実感している。
「ありがとう」
それから、仕事の話になり、なんだかんだと長引いて、当初予定した時間より大幅に遅れて帰宅した。
――疲れた。
精神的な疲労が大きい。女を振った。ただそれだけのことと、数ヶ月前の俺なら気にとめることもなかった。だが、今は違った。ふと、考えてしまう。女は傷ついただろう。気持ちにこたえてやれないのだから、同情などするのはかえって失礼だとは思うが、後味がいいものではない。人の気持ちを思うようになったのを成長と呼ぶのか、邪魔なものと思うか。
――ともかく、まず着替えよう。
ネクタイを緩めながら自室に戻る。そこで、ベッドのサイドテーブルに見慣れない小さな箱があるのに気付いた。
隣に置いてあるデジタル時計は午後十一時五十八分を表示していた。
***
「朱乃――起きているか」
日付が変わってまもなくして、聞きなれた声がした。
「はい」
返事をすると、ドアが開いて、スーツ姿の陽芽が入ってきた。帰宅して着替えることもなくやってきたのだろう。こんな深夜に、何かあったのだろうか。
ベッドに腰掛けるので、私もその隣に座った。パジャマの私とスーツの彼とが隣り合って座っている。不釣り合いな光景だ。彼はしばらく黙っていたが、おもむろに左手を膝に移動させた。手には小さな箱がある。
「俺は、甘いものは食べない。お前も知ってるだろうが、根っからの辛党だから」
箱を弄びながら、独白のように言った。
「これまでも、数えるほどしか食べたことがない。食べる必要があるもの以外はけして口にしない。だから、いつ食べたか全部覚えている」
「……」
無断で部屋にチョコレートを置いていたことを怒っているのか。いらないと遠まわしに言われているのだろう。でも、その割に声音は優しい。相変わらず視線は箱に落としているので表情はよくわからない。心拍数があがる。
「俺が今まで食べたのは、毎年、二月十四日に部屋に置かれていたモノだけだ」
――っ
「あれは全部お前だろう?」
そう言ってやっと私を見た彼は頼りなげに笑っていた。困ったようにも見えるが――照れている。
「食べてくれていたのですか?」
私が置いていることはわかっていただろう。でも、一度も「やめろ」とは言われなかった。拒否を告げることさえ面倒だったのかもしれない。それをいいことに、毎年贈り続けた。きっと捨てられているだろうけど、受け取ってもらえるだけで嬉しかった。そう思っていた。でも、食べてくれていた。
彼は私の問いには答えなかった。代わりに、
「今年は、手渡しでもらえるかと期待していたのだが」
そんな風に思っていてくれていたなんて。けれど、もう日付が変わってしまった。バレンタインは終わったのだ。でも、
「来年はちゃんと渡します」
まだ、これから先、いくらでも呆れるほど巡ってくるのだろうから。
「そうか」
髪に触れてくる指先が心地よくて静かに目を閉じた。
2010/2/4
2010/2/21 加筆修正