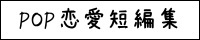
降伏せよⅢ お迎え 後編
――まいったな。
車中。泣き続ける彼女。このシチュエーションはなかなかのものだと思われた。
まいったというか、弱ったと言うべきかもしれない。初めて味わう感覚に動揺と戸惑いが強い。こういう場合、どのように対処すればいいのか。まったく見当がつかなかった。
理由を聞いても答えてくれないことが、更に事態を難解にしている。原因がわかれば取り除けばいい(取り除くことが可能であればの話だが)。しかし、わからない以上、手の出しようがない。彼女の様子を伺うが、視線を逸らして俯いたままじっとしている。話したくないということか。
とりあえず、私は運転席に戻り、車を出した。家に、戻る。それが無難に思われた。
道中は静かだった。彼女は相変わらず俯いたまま、時折、浮かんだ涙を拭っている。あまりにも可哀相なので、時々手を伸ばして頬を撫でてみる。彼女は小さく体を揺らしたが抵抗はしない。嫌われていないのは本当らしいと安堵する。
先月、エレベーターでつい田所と張り合って、彼女の機嫌を損ねてから、常に頭の片隅に存在した不安。その後で出くわしたホテルで、彼女は完全に私を無視した。もうダメかと思った。
マンションに着く。彼女は今度は素直に降りてくれた。
部屋に入る。ソファに座らせその場を後にする。キッチンでお茶を入れる。彼女が好きだと言うカモミールだ。飲むと落ち着くらしい。こんな時に最適だろう。それからホットタオルを用意した。
彼女のところへ戻る。カップを渡すと両手で受け取った。その仕草が私は好きだった。
隣に座り、右頬の少し上にタオルを押しあてる。化粧が落ちて黒くなっているのを拭うのが目的だが……意外に頑固でとれない。あまり力を入れ過ぎると肌を傷つけてしまうかもしれない。軽めに動かすが、効果がない。そうしていると、少し落ち着きかけていた彼女がまた泣きだした。思った以上に力が強かったのか。華奢な彼女には痛かったのか。私は手を止めた。
ポロポロと大粒の涙が零れる姿に、柄にもなく、キュンとした。そのような表現は忌み嫌うところだが、この時、私は紛れもなくそうなっていた。しとしとと泣く姿が、どうにもこうにも可哀相で、自然と頭を撫でてしまう。そうせずにはいられない衝動に突き動かされて、黙って撫で続けていると、彼女はますます泣いた。
「何が悲しい?」
ようやく出た問いかけに、彼女は首を横に振る。そして、持っていたマグカップを抱えたまま辛そうに、
「帰りたい」
小さな呟き。泣いている理由もわからない。おまけにこのような状態で、帰せるわけがない。
「何が気にいらない?」
「気にいらないんじゃないです……」
それだけ言うと、また、言葉を切る。一体何を言いたくないのだろうか。おそらく、重要なことなのだろう。先程は一時撤退したが、今度はそうもいかない。ここは家だし、邪魔するものはない。根気強く待つことにした。頭を撫でたり、頬を撫でたり、肩をさすってみたり、宥めながら、促す。しばらく、そうしていると、
「みっともないから」
「ん?」
彼女はようやく私を見た。そして、懺悔するように小さな声で話し始める。
「ホテルで、会った時、綺麗な人と一緒だったから。その人に、嫉妬して。だから、あなたに会うときは、せめて、私なりに、お洒落していようと思ってたのに、迎えに来るから、変な格好のまま。……さっきのお店も、いつもくるって言って。誰と来るんだろうって思って、きっと綺麗な人と来るんだろうなって。そしたら、悲しくなって。呆れられるから、泣きやまなくちゃって思っても止まらなくて。それで、ここに来たら、マスカラのとれたのを、あなたが、拭こうとしてるから。みっともない顔をしてる。恥ずかしい。帰りたい……」
たどたどしい言葉。言いながら涙がこぼれ続けるから、余計に聞き取りづらい。だが、言われている内容はハッキリと把握する。
――殺す気だろうか。
これまで仕事柄、命の危険を感じたことは幾度かあった。だが、今は本気で死にそうだ。殺人的な可愛さというのはこういうのを言うのだろう。お手上げだった。愛しいと思えば抱きしめたくなる。彼女に対してこれまでそうしてきたが、この時ばかりは、感情が飽和して体が動かなかった。この状態をどう表わせばいいか。一番近いのは、たぶん「怒り」だ。罵りたかった。ふざけるなと。私が心配して不安に思っていたことを、こんな形で返されるとは想像せず。予想外の反応が返ってくると、怒りを感じる。歓喜という憤り。それは大変始末が悪くて、もてあまし、混乱を招いている。
私が黙っているのを、よからぬ方に解釈したらしく、彼女はカップをテーブルに置くと立ち上がろうとする。帰る気なのだろう。その姿は私を呪縛から解放させた。冗談ではない。逃がさないように細い手首を掴み、そのままソファに押し倒した。
「どうやら、甘やかしすぎたようだ」
声は冷淡に響いた。彼女に向けて、このような声で話したことは当然なく、その目には恐怖の色が滲んだ。構わず、覆いかぶさるように顔を寄せた。彼女の双眸が見開かれる。
甘やかしすぎた――本当に。彼女の気持ちを大事にしようなど思わなければよかった。立場上の問題もある。無理やり傍においても、逃げ出すだろう。心ごと、手に入れるまで、ゆっくりと、着実に、と考えた自分の臆病さが嗤える。怯えていた。嫌われたくなかった。まったく私らしくない。やはり人間には性分があるのだ。普段の自分にないことをすれば亀裂が生まれる。貫き通せばよかったのだ。
「私だって同じだ。わざわざ”君”に手を出すほど困ってはいない」
車で彼女が言った言葉。
『軽い遊びで”あなたと”関係を持つほど、私はスリルを求めていない』
私とて同じだ。幾度となく繰り返してきた。やめておけ。ややこしいことになる。下手をすればこれまで築いてきたもの全て失うことになる。わかっていた。それでも手に入れた。半端な覚悟でしたわけではない。
そのまま、その甘い唇を犯した。唇から首筋、白いシャツのボタンに手をかける。はずすのもじれったく、力任せに千切る。下着も剥いで、現れた可愛らしい胸に顔をうずめる。心臓の音が早い。右が弱いことは知っている。口に含み甘噛みすると、しどけない声が漏れ、私の体が反応する。あれほど優しくしたいと思っていたのに、一度火がつくと、欲望は際限なく溢れてくる。丁寧な愛撫ではなく、快楽に引きずり込むような激しさで求める。抑え込んでいた欲求はもうとめられなかった。
彼女は、私の姿に明らかに困惑している。その顔もまたそそる。
「そんな怯えた顔をしても駄目だ。くだらない嫉妬などして先に煽ったのは君だ。二度とそんなつまらないこと思えないように、わからせてあげるから」
一度体を離し、パンツとショーツを膝下までずらし、足の間に自らの体を滑り込ませた。全部脱がせなかったのは、衣服を縄代わりに両足の開きを制限させ、身動きとれなくさせるため。抵抗はさせない。完全に私の物だとわからせる。
指で触れる。胸に与えた愛撫により濡れているが、もっと念入りに触れる。右胸に舌先、左胸に左手、下に右手を宛がい可愛がっていると、いい声が聞こえてくる。その声に聞き入って戯れていたかったが、やがて限界が近づいてくる。動きを止めて顔を見る。泣きじゃくって、その涙で化粧の黒は幾分薄まっているが酷い顔だ。それでも愛くるしくて仕方ないのだから、どうしようもない。
これ以上待てない。もう十分ほぐれた。動きは再開すると、その意味を理解した彼女が
「まって、つけてない、」
いつも細心の注意をしていることだった。私との間に子どもが出来ることは望まない。立場を考えれば当然だ。私とて、子どもがほしいわけではない。それでよかった。だが、そのことで少なからず傷ついている自分に気付いた時、私は愕然となった。だが、
「構わない」
出来たとして、それならそれでいい。いずれにせよ、もう傍から離さないと決めている。私の返答に、彼女は怯えていた。可哀相に思う。それでも覆す気はない。それを知らしめるように、
「あ……ん、やぁ……」
覆いかぶさり、体重をかけて、奥へ、沈めていく。彼女の青ざめた顔が傍に来る。私はそれに軽い口づけを繰り返し落とした。彼女は首を左右に振り、まだ静かなうちに離れてくれるようにと懇願した。
――可哀相に。
今日、何度目だろうか。彼女を哀れに思う。せめて普通の女なら、苦悩も少なかったかもしれない。私のしていることを隠し通してしまえばよかった。だが、私が選んだのは彼女だった。
「君に選択肢はない。私の傍以外に、居場所はないと覚えておきなさい」
彼女の深部を味わうように動きだすと、小さな声で「やめて」と言う。弱々しい声に、彼女の”迷い”が感じられる。完全なる拒絶ではなく迷いだ。そして、気付く。
最初から、結末は見えていたのだ。
もっと早くに奪ってしまえばよかった。どうにもならないほど身勝手に。そうしていれば、彼女の葛藤は少なかっただろう。下手な優しさなど必要なかった。それが返って仇になったのではないか。それしか選べないよう奪いきって楽にしてやればいい。恨まれてやればよかった。本当に、本気だと言うならば。自分の愚かさを呪う。
早まる動きに体が疼くのか、身動きしにくいように固定してある下肢をそれでも動かして、両膝で私のわき腹を挟み込むように締めつけてくる。甘い痴態に沈んでいく姿に込み上げてくるのは膨れ上がる執着だった。
――もう、どこにもやらない。
彼女はまだ残っている理性で、ひたすら首を振り続け抗う。その細い首筋に顔をうずめて口づける。それから、動かしたままで彼女の腰を更に密着させるように引きよせる。浮いて不安定になった状態で、いよいよ昇り詰め始めた快楽に、身をゆだねるより仕方なくなるのか、耳に届いてくるのは素直に感じる嬌声。
「ん、……あ、あ、こんのさ、……」
可愛らしい声を聞いて我慢できなくなりそうだったがどうにかこらえる。終わらせない。まだ、もう少し。ここまで焦らしても、彼女は強情だった。見かけによらず意地っ張りなところも気にいっている。私は執拗に寸でのところで交わし続ける。それで、ようやくだった。彼女から私の首に抱きついてきたので、キツく抱きしめ返す。そして最後まで。言い逃れのできない陥落だった。
その後、ベッドに場所を移してからは、ほどんど記憶がない。気付けば早朝で、抱きこむようにして眠っていた。彼女は心なしかぐったりしてやつれている。反対に、私は爽快だった。驚くほどスッキリしていて、どれほどしたのだろうかと疑う。歯止めがきかなくなるといえど、ここまで我を忘れるとは心底畏怖を感じた。流石に当面は手出しできないなと自戒する。
それから、サイドテーブルの棚を開ける。
本当は昨日渡すはずだったものだ。先月のお返し。重いだろうか。ちょっと本気過ぎて気味悪がられるのではないだろうか。どこか逃げ腰だった自分を情けなく思う。それで結局、それほど高価ではないものを選らんだ。「女の子はこういうの嫌がらないだろう」と、そんな言い訳をしながら渡す予定だった。気軽く身につけてくれたらいいと思った。こんなことなら、もっと絶望的なほど明らかに本気だと見た瞬間にわかるようなものにすればよかった。後悔する。
――弱点、なのだろうな。
そんなものが出来て、浮かれている場合ではないのに、私の唇から洩れたのはため息ではなく笑みだった。そして、箱から取り出したそれを彼女の左手の薬指にはめた。
2011/3/7