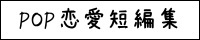
忘れた恋のはじめ方 3
キレているとわかっても、特に怖いとは思わなかった。久しぶりだなぁ、とどこか懐かしくさえ感じられた。学生時代、よくこうして怒らせた。「仏の都々木」と呼ばれるくらい、人当たりが良く、誰にでもいい顔をする男だったが、私には例外だった。繰り返すけれど、私は都々木を苛めていたから。都々木を拗ねさせたり、ふてくされさせたり、他の人には見せない顔をさせることで、優越を感じたかったのかもしれない。恋愛出来ない女の、つまらない当てこすりだ。思い出すと胸が軋む。馬鹿なことをしていた。
ただ、あの頃は確信犯だったが、今回は思い当たる原因がない。
何を怒っているのだろうか。
お気に召さないことをしたのだろうけれど、ピンとこない。もしかして私は、故意に何かをしなくても、都々木とは相性が悪いのかもしれない。自然にしていても怒らせてしまうのかも。と、思っていると、
「竹村?」
考え込んで返事をしなかったからか、先程の不機嫌な声とは打って変わって今度は頼りない声で私の名を呼んでいる。私は我に返って、
「なんか懐かしいなぁ、と思って」
「は?」
「昔、よく怒らせたから。あの頃のことを思い出してた」
「そう言えば、お前には腹が立つことが多かった」
「うん。でも、あれはわざとだったんだよ」
言うつもりはなかったのに、ポロリと漏らしてしまう。酔っているからだろう。そんないい訳を自分にしながら私は笑う。だけど、都々木は
「はぁ? 何だよそれ。なんでそんなことすんの?」
突然、そんな告白をされれば、当然そうなるか。私はさらに笑いながら、
「あんたのこと好きだったけど、ずーっと彼女がいたし、恋愛ごとは苦手で、だから、そうやって怒らせて気を引いてたんだよ。好きな子を苛めるっていうやつ? 思い出したら、まったく馬鹿な真似をしてたなって。ごめん」
言い終えると、電話越しに小さくつぶやく声が聞こえたが、遠くて聞きとれない。「何?」と尋ねると、
「ムカつく。今のが過去の全てを比較して一番ムカついた」
一度は引いていたはずの怒りが再燃したのか、また不機嫌な――というかさっきよりも激情している声だ。私はビックリした。謝っているのに。いや、でも、謝っても許されないことはあるか。
それにしても、今までで一番ムカついたって。やっぱり私は普通にしていて都々木を怒らせてしまうようだ。これは、たとえ私にものすごく恋愛スキルがあったとしてもうまくいかなかったのだろうなぁ、としんみりする。もし付き合えていたとしたら、えげつないことになって、二度と顔も見たくないような別れに繋がっていたかも。懐かしむ思い出のまま終わってよかった。と、初めて思った。
「……ごめん。悪かったよ。笑い話にするようなことじゃなかったね。いじめた方は忘れても、いじめられた方は忘れないって言うもんね。過去のこ」「だからそれをやめろ」
言葉を途中で遮られて、私は黙った。こんな風に、都々木が人の話に割り込んでくることは、私の記憶ではなかった。私が怒らせるようなこと言って、不機嫌にさせた時でも、都々木は私の言葉を最後まで聞いてから言い返してくる。「ムカつく」「腹立つ」と言いながらも、まくしたてるように苛立ちをぶつけて、私の全てを、人格そのものを否定するようなことはなかった。「それについては」、というスタンスを通していた。私は都々木のそういうところが好きだったのだ。それが、
――どうしよう。
知らない。こんな風な怒りを見せる都々木を。
それまで、どこか余裕があった私の心は真っ黒に塗りつぶされていた。
自分の発言を反芻してみる。何がそれほど都々木の琴線に触れたのか。どれがいけなかったのか。だけど、よくわからない。わからないから、余計に混乱する。何か言葉を発すれば、また怒らせるかもしれない。下手なことは言えない。押し黙るしかない。どうしよう。繰り返すのはそのフレーズばかりだ。
充電がなくなったことにして、切ってしまおうか。
思いついたのは、あまりにも卑怯な逃げだった。怒らせるだけ怒らせて、それはない。でも――と、私の不穏な空気を読みとったのか、電話口からはため息が聞こえた。
「……俺、お前に『付き合ってくれ』って言ってんだけど?」
声音からわずかに怒りの色が引いていたが、その分、躊躇いが増しているように感じられた。それから更に、
「それなのに『あの頃』とか『過去』とか全部終わってます、みたいな言い方しやがって。なんなの? それ、遠まわしに俺とは付き合えませんって言ってんの? 今日だって、久々に会ったのに、それもお前に告白した後だってのに、普通すぎだし。まったくそのことには触れてこないし。なんなの?」
一息にそこまで言われた。
流れ込んできた言葉は、私の体内を駆け巡り、感情を置き去りにしたままで、頭だけが妙に冴えて、猛スピードで処理されていく。都々木が怒った理由。その件についてはまだ納得できるものではある。ただ、会ってからお店での一連を責められるのは違うだろう。
「あんたが話があるって呼び出したんだから、あんたが自分で切り出してくるまで、こっちからは聞けないでしょう? それなのに、どうして私が責められなきゃならないの?」
「俺は告白したんだ。返事を待つ身なんだから、俺から言えるはずないだろう!」
「告白なんてされてないよ」
「はぁ? したじゃねぇか。電話で、『付き合ってくれ』って言っただろうが。俺は会ってから言うつもりだったのに、お前が言わなきゃ会わないとか駄々こねるから、電話で告白したろーが」
「駄々なんてこねてないわよ。そう言った方が、言いやすいかと思っただけで……というか、あんなの告白じゃないじゃん」
「……意味分かんないけど」
都々木は機嫌をますます低下させて言った。だから、私は詳細に説明する。
「別に好きって言われてないし。最初に『頼みごとだ』って言ってたし。だから事情があって、そんなことを言いだしたんだなぁって思った。会ったら話をしてくるんだろうなって。それに、今日会ったときだって、全然普通だったのあんたの方じゃない。それなのに私が一人で意識するのも変だから普通に接したんだよ」
そうだ。あの態度は、どうみても普通だった。私を好きだとしたら、少しぐらい照れくさがったりしてもいい。だけど、そんな様子わずかも見られなかった。
「けど、お店入ってすぐ不機嫌な顔になったから、私の顔を見たら、やっぱり頼むのはやめようって思ったのかと。お眼鏡にかなわなかったんだなぁって。だったら、話題には触れずに、知らない振りをしておいた方がいいと思ったんだよ。話を振ったら逆に困るんじゃないかって、配慮だよ」
「……っんだよそれ」
私の言い分に、だけど都々木は納得どころか、苛立ちを募らせただけだったようで、
「俺は……、俺はなぁ、」
怒りなのか、混乱なのか、声が震えている。
続きを待つと、
「一年前、お前に好きだって言われてから、ずっとそのことが頭から離れなくて、付き合ってた女にも『心が上の空だ』って詰め寄られて振られるし。その後だって、何人かに告白されたけど、付き合う気にはなれないし。彼女がいない時に告白されたら、とりあえず付き合ってみるってのが俺のポリシーだったのに、それも出来ない。全部お前のせいだ。なのに、当の本人はすっかり俺のことなんて過去のことで、ふざけんなよ」
聞かされた内容に、私はクラクラした。でも、都々木の言うことは、やはりどこかピントがぼやけているというか、肝心な言葉は相変わらず抜け落ちている。意味するところはわかるけれど、私もそれほど自分に自信があるわけではないし、経験豊富でもないし、自惚れて恥をかきたくないプライドだってある。ただ、
「ねぇ、あんた、もしかして、告白、したことないの?」
電話の向こうで、明らかに息を飲んだのがわかった。
いつだって告白されてきたから、自分から告白することはなかった。だから、こんな風なわけのわからないことになっているのではないか。モテ男の弊害。恋愛の経験は豊富そうに見えて、内情は女の子に甘えた恋愛をしてきただけではないか。
そこまで考えて、腑に落ちることがある。
都々木はモテるけれど、遊び人ではなかった。彼女がいる時は、彼女一筋だった。だけど、付き合うサイクルは長くない。そのことを、ちょっと不思議に思っていた。男前で誠実なのにどうしてすぐに別れてしまうのだろうか。それも話に聞くところによると、都々木が振られるらしい。もしかして私が知らないだけで、陰では遊びまくって、浮気しまくっていて振られるのだろうか。それとも、振られたという言い方をしているだけで、ものすごく飽き症で、本当は都々木の方から振っているのだろうか。そんな風に想像して、なんとなくそれで納得していた。だけど、そうではなくて、恋愛において女性に任せっぱなしだったのではないだろうか。女性を楽しませるというタイプではない。黙っていても相手が寄ってくるから。そういう怠慢に、彼女たちは嫌気がさして別れを告げたのではないか。
この男は、実は恋愛下手ではないのか。
男前だから、彼女が途絶えたことがないから、モテるから、恋愛上手だとは限らない。
「好きな相手に、ちゃんと好きだと言えない、ダメ男なんじゃないの?」
もっとハッキリと告げてみると、
「……! やっぱりお前ムッカつくわ〜。まじでムカつくわ。ムカつく。あんまりにもムカついたから、これから会いに行く。待ってろよ」
そう言うと、電話が切れた。
私はただ茫然として、通話終了と出ている画面を凝視する。
待ってろよって何? ここで待てってこと? っていうか、都々木は……、と思っていると、案の定、再び携帯が鳴る。ディスプレイには都々木創の文字。出ると、名乗りもせず、不機嫌な声で、
「ってお前、今どこにいんの? どこに住んでんの? 何駅に行けばいいわけ?」
「何も知らないくせに電話切ったの? バッカじゃないの?」
「うるせぇ、とっとと教えろよ。話は、会ってからだ」
呆れた、と私は呟いて、それから駅の名前を告げると、懲りもせず「待ってろよ!」と決まらない啖呵を切って電話が切られる。バッカじゃないの? と私も繰り返し思う。
なんなのだろうか、この展開。なんなのだろうか、あの男。
だけど。
なんなのだろうか、この胸の甘い疼きは。
あばたのえくぼ。恋は盲目。惚れた欲目。そういうことはある。だけど、私のそれは一年も前に終わったはずの感情だった。だからきっと、その効果は出ないはずだ。情けない面を見せつけられたら、「ああ、こんな男と付き合わなくてよかった。好きだったのは気の迷いだ」と思ってもいいぐらいだ。それなのに、私の心に去来しているのはじんわりとした温もりであり、こそばゆい高鳴りであり、奥歯でかみ殺す喜びだった。
まだ、わからないけれど。
会って、今度こそちゃんと話をしてみないことには、何とも言えないけれど。踊りだしそうな感情だけで突っ走れるほど、私は足腰が丈夫ではないから。でも、きっと――。
改札を振り返る。
まだ、電車の到着を知らせるアナウンスは流れない。私はそれが聞こえるのをじっと待つ。【完】
2011/7/23